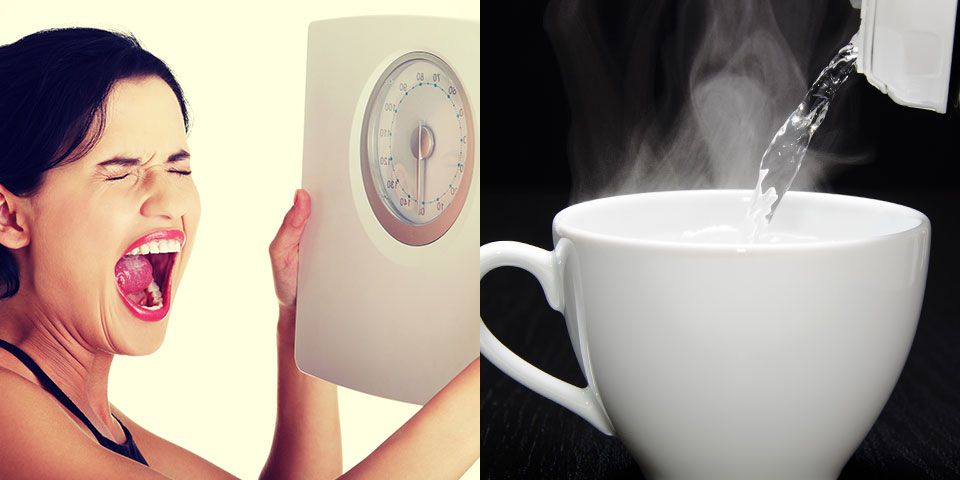解説
冷えの原因
冷えるとお腹が痛くなったり、下痢をしたり…ということは、誰でも経験したことがあるのではないでしょうか?冷えは、その種類によって「急性の冷え」と「慢性の冷え」の2つに分けることができます。
「急性の冷え」は冷たいものを急にたくさん飲んだり、エアコンの冷たい風に直にあたったりした場合に起こる冷えです。「慢性の冷え」は体内で熱を作り出す能力が落ちていることによる冷えを指します。熱を生み出すのは筋肉ですから、一般的に筋肉量の少ない女性の方が冷え症の人が多いのです。

どうして冷えが腹痛を引き起こすのか
では、どうして冷えが腹痛の原因となるのでしょうか。身体は冷えを自覚すると、身体を温めようといろいろな調整を行います。その1つは自律神経による調整です。自律神経は筋肉を意識して動かす指令を出す運動神経とは異なり、無意識的に身体のバランスを整えて生命を維持するために働いている神経です。例えば心臓の拍動数を変えたり、汗をかいたりといった働きは自律神経によるもの。腸を動かすのも自律神経の役目です。
通常はリラックスしているときに自律神経の1つの副交感神経が働いて、唾液や胃液を分泌し、食事を消化するために腸を動かしています。ところが、自律神経失調になると食事の時間ではないときに腸を動かしてしまったり、逆に腸を動かさなければいけないときに動きが悪くなってしまう、といったことが起きます。体温の調節も自律神経が担っているので、冷えが続くと自律神経が行っている腸の調節がうまくできなくなってしまうのです。
それだけでなく、身体を温めようとして腹痛が出ることもあります。冒頭で身体の熱を作るのは筋肉と説明しましたね。筋肉と聞くと腕や脚を動かす骨格筋をイメージする人も多いかと思いますが、腸を動かすための筋肉もあります。身体が冷えを感じると、腸を動かす筋肉も活発に働かせて熱を作り出そうとするのです。このように腸が過剰に動きすぎると、お腹にキリキリするような痛みが生じるおそれがあります。
さらに、冷えは腹痛だけでなく、人によっては下痢を引き起こすこともあります。これも身体を温めようとする働きが原因の1つ。というのも、少しでも腸の内容物を減らして、温めなければならない身体の体積を小さくし、熱を血液に早く伝えて温めようとしているのです。これは、プールなどで身体が冷えたときに、トイレで排尿して水分を減らそうとするのと同じ原理なのです。

冷えを予防するために
つまり、冷えによってお腹が痛くなるのは、できるだけ体温を元に戻そうとする身体の働きだといえます。ですから、予防で大切なことは身体を冷やさないことです。暑いときでも、フローズンドリンクのような腸がびっくりするほど冷たいものを飲むのは避けましょう。またエアコンの風が直に身体にあたらない位置に座るようにしたり、部屋が冷えているときは温かい飲み物を飲むようにしましょう。身体をきつく締め付けるような衣服も冷えの元になるので避けた方がいいでしょう。
冷えによって腹痛や下痢が起きているときには、外から積極的に温めることも効果があります。看護の現場では蒸しタオルなどで身体のつらい部分を温めて症状を和らげる手法が使われています。市販の温感シートを使ったところ、若い女性でトイレの回数が改善し、温かくてよく眠れたという報告があるなどの効果もみられています。冷えを撃退してすっきりしたお腹で過ごしましょう。

<参考文献>
■日本看護技術学会誌
『湿熱加温の健康な若年女性の排尿回数およびQOLへの影響』
執筆 : 医師 春田萌
編集 : my healthy(マイヘルシー)編集部
統計データ
できるだけ体を冷やさないような生活をおくっていない人は、月に1回以上、腹痛になりやすくなるリスクが1.42倍になります。
A: できるだけ体を冷やさないような生活をおくっていますか?
B: 月に1回以上、腹痛になりますか?
| A | |
|---|---|
| はい | いいえ |
|
58.0%
609人 |
42.0%
441人 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| はい | いいえ | はい | いいえ |
|
21.43%
225人 |
36.57%
384人 |
19.05%
200人 |
22.95%
241人 |
| Z検定値 | 2.74 |
|---|---|
| オッズ比 | 1.42 |
| 信頼度 | 99.3% |
- ・オッズ比
AをしないとBになるリスクがX倍になることを示しています。 - ・信頼度
信頼度はデータの関連性の正しさを表しています。
(統計学のZ検定を使用)
>数値の見かたはこちら