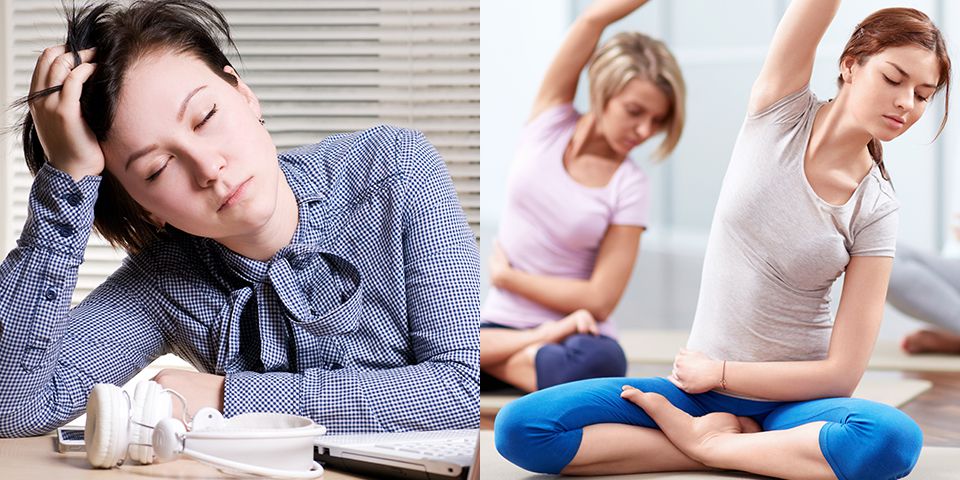解説
身体が硬い人は増えている
最近、身体が硬い人が増えています。驚くことに大人だけでなく、小学生でも身体の一部分が硬いということが増えているのです。
身体の柔軟性には、関節がどの範囲まで動くかを指す“静的柔軟性”と、動いたときにどのくらい素早くなめらかに動けるかを指す“動的柔軟性”の2種類があります。
「身体が硬い」とは、一般的に静的柔軟性が低いということを意味しており、この柔軟性は筋肉や腱が伸びる力を反映しています。例えば、肩の柔軟性であれば両手が背中側でくっつくかを見てみましょう。右手を上から、左手を下から回して、背中側で触れるかを見ます。次に左右逆で試してみましょう。
また、下半身の柔軟性は足をかかとまでしっかりつけて、おしりを落とし、しゃがみこめるかどうかで判断できます。途中でかかとが浮いたり、後ろにしりもちをつくようであれば、下半身の柔軟性が落ちている可能性があります。
小学生の場合をさらに分析すると、一日中家にこもってスポーツを全くしていない子には、やはり柔軟性の低下がみられました。それだけでなく、運動クラブなどに参加して積極的にスポーツをしていた子にも、柔軟性の低下が認められたのです。その原因としては、特定のスポーツで使う筋肉だけを鍛えすぎるため、身体のバランスが崩れていることが考えられます。
では、柔軟性を高めるためにはどんなことが有用でしょうか?一般的には、柔軟性向上のためにストレッチがよく行われていますね。ストレッチには柔軟性を高める効果が十分にあります。ストレッチによる柔軟性向上の効果をよりいっそう高めるために、ストレッチを行う際には、お風呂に入った後など身体が温まったときに行うとよいとされています。これは、身体が温まると筋肉や腱が伸びやすくなるからです。では、ほかに身体を温める方法はないでしょうか?そこでシナモンの登場です。

シナモンが血管の柔軟性を改善し筋肉を温める
シナモンは“ニッキ”とも呼ばれ、肉桂の皮をはぎ取って乾燥させたものがシナモンスティック、粉にしたものがシナモンパウダーです。シナモンは漢方薬としても使用されており、“桂皮(けいひ)”とも呼ばれます。シナモンには血管年齢を下げたり、動脈硬化を改善したりする効果があるのです。血管年齢が下がり、動脈硬化が改善されれば血液の流れもよくなります。すると、筋肉の隅々まで血液が届きやすくなるので、筋肉が温まりやすくなります。
一方、シナモンを過剰摂取すると、シナモンに含まれる“クマリン”という成分により、肝臓を悪くすることがあるという警告があります。しかし、東京都の調査によれば、日本人が通常食べるスパイスをすべてシナモンにしたとしても、健康上の問題が起きるほどのクマリン摂取にはつながらなかったとされています。つまり、シナモンなどのスパイスを常識的な範囲で楽しむのであれば、クマリンの量はそれほど気にしなくてもよいということですね。
シナモンはハーブティーに加えたり、リンゴのお菓子に入れたりと、さまざまな食べ方で香りを楽しめるスパイスです。身体が硬いと思ったら、シナモンを食事に取り入れて身体を温め、ストレッチを始めてみましょう。

<参考文献>
■タケダ健康サイト
『「シナモン」でおなじみ!桂皮 ケイヒ』
■東京都健康安全研究センター研究年報
『シナモン含有食品のクマリン分析法及び実態調査』
■NHK クローズアップ現代+
『子どもの体に異変あり〜広がる“ロコモティブシンドローム”予備軍〜』
執筆 : 医師 春田萌
編集 : my healthy(マイヘルシー)編集部
統計データ
月に1回以上、シナモンを食べていない人は、同年代の人よりも体が硬くなりやすくなるリスクが3.95倍になります。
A: 月に1回以上、シナモンを食べていますか?
B: 同年代の人よりも体が硬いですか?
| A | |
|---|---|
| はい | いいえ |
|
7.8%
24人 |
92.2%
285人 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| はい | いいえ | はい | いいえ |
|
1.94%
6人 |
5.83%
18人 |
52.43%
162人 |
39.81%
123人 |
| Z検定値 | 3.01 |
|---|---|
| オッズ比 | 3.95 |
| 信頼度 | 99.7% |
- ・オッズ比
AをしないとBになるリスクがX倍になることを示しています。 - ・信頼度
信頼度はデータの関連性の正しさを表しています。
(統計学のZ検定を使用)
>数値の見かたはこちら