解説
1日の始まりの朝食!脳にブドウ糖を補給しよう
ダイエットや健康維持のために毎日の食事に気を配っている人でも、「1日の目標カロリー以内で食べさえすれば、1日に2食でも問題ない」と思っている人は多いかもしれません。ですが、それは大きな落とし穴。
朝食を抜いて、「昼食と夕食の2食で目標摂取カロリー内に抑えるから大丈夫」と考えているのかもしれませんが、その方法では脂肪をためやすくなる身体になってしまいます。そのため、一時的に痩せてもリバウンドしやすくなったり、体調を崩してしまったりと、かえって身体の調子が悪くなってしまうおそれがあるのです。
また、食べない人は、大事なときにミスが多くなる可能性もあります。1日の始まりである朝食を毎日とることは、仕事においても、勉強においても非常に大事なことなのです。
朝食をとることの重要性について、一緒に考えてみましょう。まず、私たちの身体は、1日24時間の生活の中で時間を感じ、身体の働きをコントロールしています。例えば、朝になれば目覚め、夜になれば眠くなるなど、自然と身体の中で一定のリズムが働いています。この体内リズムをしっかり働かせ、身体の調子を整えるためには、朝食を食べることがとても大切です。
朝食を食べないと、脳のエネルギーが不足してしまいます。すると、イライラしたり集中力が低下したりしてミスを起こしやすくなり、勉強や仕事のパフォーマンスが落ちてしまうおそれがあります。脳が活動するために必要な栄養素はブドウ糖。このブドウ糖は、脳にため込んでおくことができません。また朝食を抜いてしまうと、脳が栄養不足で体調が悪い、集中力が切れるなど、生活の質の低下を招くこともあるのです。
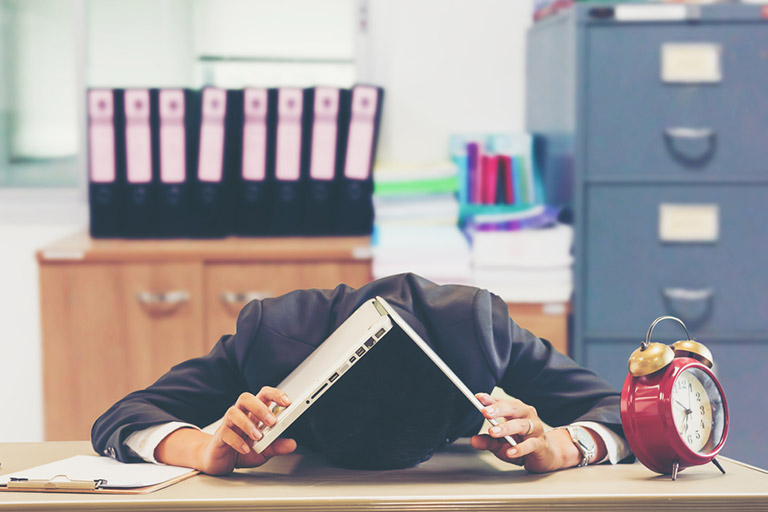
代謝に必要なビタミンB群もあわせてとろう
朝食をしっかりとることは、脳のエネルギー不足を解消し、大事な場面でのミスを回避することにつながります。脳のエネルギー源になるブドウ糖は、ご飯やパンなどといった炭水化物(糖質)から作り出すことができるので、主食をしっかり食べることを心がけましょう。それだけでなく、糖質の代謝に必要なビタミンも一緒にとることが大切です。特にビタミンB1、B2、B6、B12などのビタミンB群を多く含む食品を、朝食にしっかりとり入れましょう。
ビタミンB群は、豚肉や納豆、レバー、牛乳、アジ、鮭などの食品に多く含まれています。主食には、パンよりもご飯がおすすめ。ご飯はパンと比べて、ブドウ糖を長時間脳に送ることができる、腹持ちがよくダイエットにも効果的といったメリットがあるのです。日本の伝統的な朝食は、ご飯を主食として、たんぱく質の肉や魚、大豆製品、野菜などの食品を合わせたもの。つまり、日本の伝統的な朝食は、栄養不足を解消しつつ、脳を活性化して集中力をアップさせるためにベストな朝食といえるでしょう。
また、食事は1日2回よりも3回とる方が血糖値をゆっくり上昇させるので、血糖値を安定させることができます。そして中性脂肪やコレステロールも増えにくくなります。血糖値が高いと、日中に強い眠気が生じて集中を欠く原因にもなってしまいます。忙しい毎日を送っている人も多いとはいえ、できるかぎり食事の回数を規則正しく1日3回にすることが大切です。
朝食を全く食べる習慣がないという人は、まずはバナナやヨーグルトなど軽めの食べやすい食品から始め、少しずつ慣れてきたら主食などをプラスしていきましょう。大切な場面でミスをしないようにするためにも、朝食を毎日しっかりとることを心がけたいですね。

<参考文献>
■厚生労働省
『平成27年 国民健康・栄養調査結果の概要』
■農林水産省
『朝ごはんを食べないと?』
執筆 : 管理栄養士 高橋美枝
編集 : my healthy(マイヘルシー)編集部
統計データ
朝食を食べるようにしていない人は、大事なときに、ミスが多くなるリスクが2.16倍になります。
A: 朝食を食べるようにしていますか?
B: 大事なときに、ミスが多い方ですか?
| A | |
|---|---|
| はい | いいえ |
|
73.1%
226人 |
26.9%
83人 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| はい | いいえ | はい | いいえ |
|
17.8%
55人 |
55.34%
171人 |
11.0%
34人 |
15.86%
49人 |
| Z検定値 | 2.86 |
|---|---|
| オッズ比 | 2.16 |
| 信頼度 | 99.5% |
- ・オッズ比
AをしないとBになるリスクがX倍になることを示しています。 - ・信頼度
信頼度はデータの関連性の正しさを表しています。
(統計学のZ検定を使用)
>数値の見かたはこちら
















