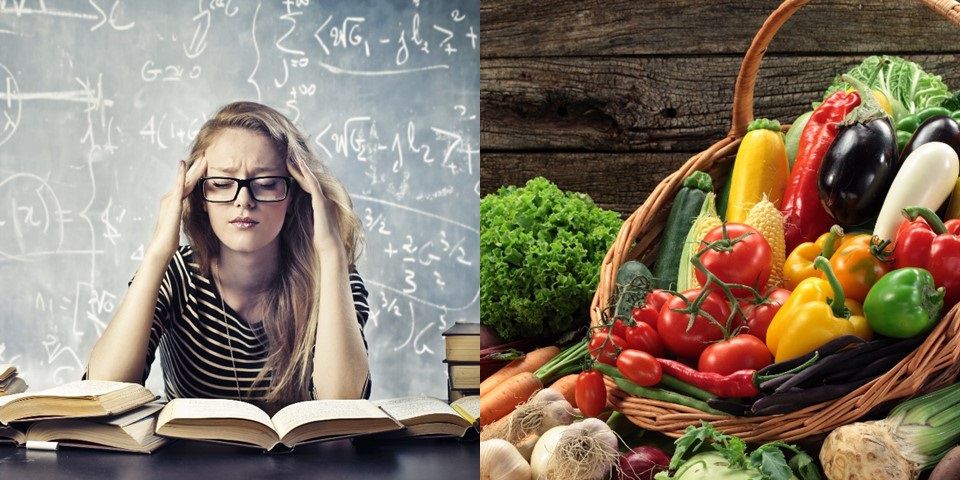解説
集中力を高める方法
集中力が必要な人の代表といえば、受験生。受験生の夜食というと、うどんのように温かくて消化のよい食事をとっているイメージがありますが、実はもっとおすすめしたいのが生のフルーツです。その理由を、これから解説しましょう。
集中力を上げるために必要なのは、脳に栄養が十分行き届いていること、脳の疲れがすぐとれること、脳の中の情報伝達がスムーズに行われること、そして脳を刺激することです。フルーツは、集中力を高めるために必要であるこれらの要素を兼ね備えているのです。

それぞれのフルーツの効果
フルーツには集中力を高めるために必要な栄養素が豊富に含まれています。では、どのような成分が集中力向上に効果が期待できるのでしょうか。
まず、フルーツの甘みの1つである“ブドウ糖”。脳の栄養として使えるのは糖質の中でもブドウ糖だけです。お腹が空くと頭もボーっとしてしまいますね。これはブドウ糖不足の状態です。フルーツにはブドウ糖がたくさん含まれているので、脳の栄養として即効性があります。ちなみにうどんの場合、炭水化物からブドウ糖に変わるまで時間がかかります。
集中力の低下とともに目の疲れを感じている場合には、ブルーベリーのアントシアニンやルチンが効果的。集中するには、目を使って文字などから情報を得るプロセスが欠かせません。現代人はパソコンやスマホで目を酷使していることが多くなります。目は細かな筋肉でピントを調整していますが、その司令塔として働いているのは脳です。ですから、目が疲れると脳も疲れて集中力が下がってしまうのですね。
アントシアニンには目の機能を改善する効果が、ルチンには目の組織を支えているコラーゲンなどを保護する働きがあるとされています。疲れ目を防ぐためにも、ブルーベリーやカシス、ブドウなどをとることをおすすめします。
同じように、現代人が不足しがちなのはストレスで消費されるビタミンCです。悩み事があるとそれが気になってしまい、集中力が上がらない…ということは誰でも経験したことがあるのではないでしょうか。ビタミンCをとることはストレスへの抵抗力を高めてくれます。さらにビタミンCには貧血を予防する効果があり、脳への血流を維持することで集中力を高める効果があります。オレンジなどのかんきつ類やキウイなど、フルーツにはビタミンCが豊富です。
また、イギリスの実験では、フルーツには糖分以外にも集中力を高める効果がある成分が含まれている可能性が示されています。この研究では、オレンジジュースを飲んだグループと砂糖水を飲んだグループとの集中力の違いを比較しており、実験の結果、オレンジジュースを飲んだグループは、オレンジジュースを飲んでから6時間ほどの間、継続して注意力が高くなり、反応スピードも速くなったことがわかりました。この作用をもたらした成分については、オレンジに含まれているフラボノイドではないかと考えられています。
さらに、フルーツには酸味や香りによって五感を刺激する事で脳の活性化を促したり、身体をリラックス状態にするのを促したりする効果があります。また、バナナには脳で情報を伝える物質の元になるトリプトファンが含まれていて、集中力に関わるセロトニンを増やす効果があります。
フルーツから得られる効果は、フルーツの種類によって異なりますが、彩りもきれいな季節の生フルーツを食べることで気分をリフレッシュする効果もあります。集中力を高めたいときには、ぜひ試してみて下さいね。

<参考文献>
■University of Reading
『GLASS OF OJ A DAY BOOSTS ALERTNESS AND CONCENTRATION』
■European Journal of Nutrition
『Flavonoid-rich orange juice is associated with acute improvements in cognitive function in healthy middle-aged males.』
執筆 : 医師 春田萌
編集 : my healthy(マイヘルシー)編集部
統計データ
週に3回以上、生のフルーツを食べていない人は、集中力が続かなくなるリスクが1.43倍になります。
A: 週に3回以上、生のフルーツを食べていますか?
B: 人よりも集中力が続かないほうですか?
| A | |
|---|---|
| はい | いいえ |
|
32.3%
432人 |
67.7%
905人 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| はい | いいえ | はい | いいえ |
|
11.44%
153人 |
20.87%
279人 |
29.69%
397人 |
38.0%
508人 |
| Z検定値 | 2.94 |
|---|---|
| オッズ比 | 1.43 |
| 信頼度 | 99.6% |
- ・オッズ比
AをしないとBになるリスクがX倍になることを示しています。 - ・信頼度
信頼度はデータの関連性の正しさを表しています。
(統計学のZ検定を使用)
>数値の見かたはこちら