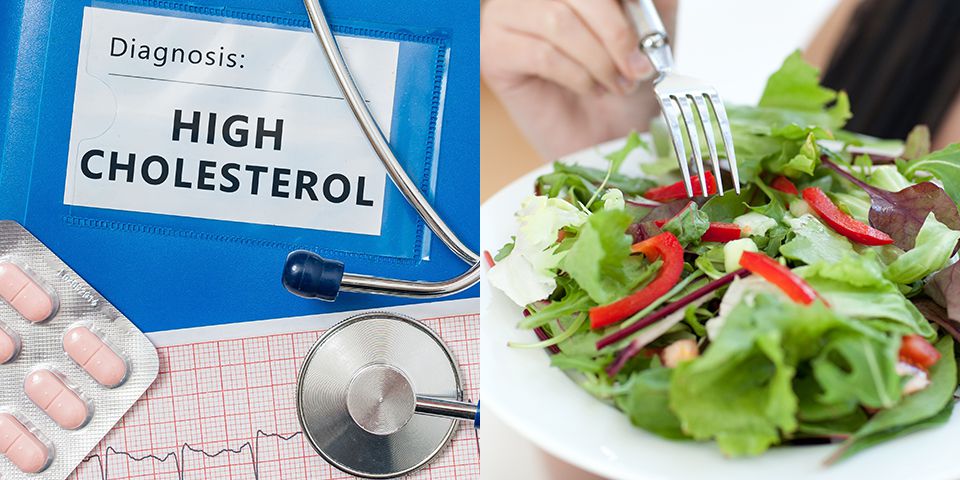解説
悪玉コレステロールには、血管の錆びつきを取ることが大切
悪者というイメージが強いコレステロール。健康診断でコレステロール値を注意された人も少なくないでしょう。しかし、コレステロールは、本来は身体の細胞の一部やホルモン、消化液などの材料になり、身体にとって欠かせないものです。
コレステロールには、“LDLコレステロール”と“HDLコレステロール”の大きく分けて2種類があります。世間一般に悪者と思われているのは“LDLコレステロール”。LDLコレステロールが血液中に多くありすぎると、LDLコレステロールは血管の壁に入り込み、そこにたまっていってしまいます。すると、その部分の血管が狭くなるため、血液が流れにくくなり、血管が詰まって動脈硬化を招くリスクが高くなるというわけです。このことから、「コレステロール=悪者」というイメージがついてしまったのでしょう。
動脈硬化は目立った自覚症状がほとんどありません。自覚症状がないまま心筋梗塞や脳梗塞といった深刻な病気を引き起こしてしまうおそれがあるため、動脈硬化は「サイレントキラー」ともよばれています。動脈硬化を予防するためには、血管を詰まらせる原因となるLDLコレステロールを減らす必要があります。LDLコレステロールを減らすには、余分なコレステロールを排出する“HDLコレステロール”を増やすことが大切です。
それだけなく、“酸化LDL”というより凶悪化してしまったLDLコレステロールにも注意が必要です。酸化LDLは、LDLコレステロールが活性酸素などによって酸化されることによって生じたものです。酸化LDLは、もとのLDLコレステロールよりも血管を傷つける作用が強く、血管の壁に蓄積しやすいという性質があります。ですから、もとのLDLコレステロールよりもやっかいなコレステロールなのです。
では、酸化LDLを減らすにはどのようなことに気を付けたら良いのでしょうか?実は、その答えは緑黄色野菜にあります。
緑黄色野菜には、抗酸化作用が強いβ-カロテン、ビタミンE、ビタミンC、ポリフェノール、リコピンなどの栄養素が含まれています。こうした野菜の栄養は、活性酸素を除去する働きがあるため、LDLコレステロールが酸化LDLに変わるのを防いでくれるのです。酸化LDLの量を増やさないことで、血管が詰まるリスクを減らし、動脈硬化といった症状や心臓病などの深刻な病気の発症を予防することが期待できるというわけです。

あぶらで変える血管の健康
緑黄色野菜には、ビタミン、ミネラルだけでなく食物繊維が豊富に含まれています。食物繊維はコレステロールの吸収を抑えてくれるため、食事からコレステロールをとりすぎないようにすることができます。味噌汁にたっぷり野菜やきのこを入れるとカサも減りたくさん食べられますので、毎日、味噌汁を献立にプラスするのも良いでしょう。
コレステロールのバランスを正常にするには、「あぶら」のとり方がカギになります。LDLコレステロールを増やしてしまうのは、バターやラード、肉の脂身や生クリームなどの動物性の脂肪です。マーガリンやショートニングなど、材料は植物性の油ですが、加工の段階でLDLコレステロールを増やす元になる“トランス脂肪酸”が増えてしまっています。
一方で、オリーブオイルやごま油などの植物性の油や、青魚の油は積極的にとりたい種類です。緑黄色野菜に多く含まれるβ-カロテンは、油によって吸収率が高まるため、炒め物やソテーなどの調理法がおすすめ。炒め物やソテーをするときには、質の良い植物性の油を使ってくださいね。
豆腐や納豆などの大豆製品、青魚もLDLコレステロールを減らし、HDLコレステロールを増やしてくれる食品です。肉や動物性脂肪を食べることが多く、魚や豆腐、納豆などの料理が少なかった人は、献立の見直しをしてみましょう。また、適度な運動で血管の柔軟性をとり戻すことができます。ストレッチやウォーキングをとり入れて、血管をしなやかに保ちましょう。

<参考文献>
■厚生労働省 e-ヘルスネット
『緑黄色野菜(りょくおうしょくやさい)』
■国立循環器病研究センター 循環器病情報サービス
『[85] 「脂質異常症」といわれたら』
執筆 : 管理栄養士 高橋美枝
編集 : my healthy(マイヘルシー)編集部
統計データ
週に3回以上、緑黄色野菜を食べていない人は、コレステロール値が基準値を超えやすくなるリスクが1.67倍になります。
A: 週に3回以上、緑黄色野菜を食べていますか?
B: コレステロール値は基準値を超えていますか?
| A | |
|---|---|
| はい | いいえ |
|
74.0%
549人 |
26.0%
193人 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| はい | いいえ | はい | いいえ |
|
13.07%
97人 |
60.92%
452人 |
6.87%
51人 |
19.14%
142人 |
| Z検定値 | 2.62 |
|---|---|
| オッズ比 | 1.67 |
| 信頼度 | 99.1% |
- ・オッズ比
AをしないとBになるリスクがX倍になることを示しています。 - ・信頼度
信頼度はデータの関連性の正しさを表しています。
(統計学のZ検定を使用)
>数値の見かたはこちら